こんにちは!
全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!
御朱印帳づくりに携わる者として、もっと御朱印集めが楽しくなるように、訪れた寺社仏閣の魅力や、私たちが手がける御朱印帳のこともお届けしています。
今回訪れたのは、奈良県桜井市にある「大神神社」。読み方は「おおみわじんじゃ」です。日本最古の神社といわれ、本殿を持たず、背後の三輪山そのものをご神体として仰ぐ独特の信仰を今に伝えています。山を拝するという古代の神まつりの姿が息づく境内に立つと、神秘的な空気に包まれるのを感じます。
また、過去には有名スピリチュアル・カウンセラーがテレビ番組で「国内最強のパワースポット」と絶賛したことでも知られており、全国から多くの参拝者が訪れる人気の聖地でもあります。
この記事では、大神神社の歴史や見どころ、そして実際に参拝して感じた魅力を、写真やエピソードを交えながらレビューしていきます。
大神神社のご祭神・大物主大神(おおものぬしのおおかみ)は、『古事記』や『日本書紀』で蛇の姿に化身したと伝えられています。特に有名なのが「三輪山の大物主が美しい娘のもとに白蛇の姿で通った」という神話。蛇は大物主大神を象徴する存在として、今も信仰されています。そんな神話にちなんで、参拝にぴったりの御朱印帳がこちら。
大神神社参拝に持参したい御朱印帳
白蛇皮風御朱印帳

まるで本物の白蛇の鱗のように美しい型押しが施された特別仕様の一冊。上質な奉書紙を使用した蛇腹式で、墨の乗りや発色も良く、御朱印を鮮やかに残せます。丈夫な作りで持ち歩きやすく、日本製ならではの丁寧な仕上がりも魅力です。
白蛇は古来より「金運・開運・繁栄」の象徴とされ、大物主大神の神話とも深く結びついています。大神神社を参拝し、白蛇のご加護を感じながら御朱印をいただくにはぴったりの御朱印帳です。
この御朱印帳が気になる方は、Amazonや楽天市場でも取り扱っています。気軽にのぞいてみてください。
それでは、大神神社の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。
大神神社のアクセスと基本情報
【大神神社の所在地】
〒633-8538 奈良県桜井市三輪1422
【大神神社の電話番号】
0744-42-6633
【大神神社へのアクセス】
JR桜井線(万葉まほろば線)「三輪駅」から徒歩約5分
【大神神社の駐車場】
大神神社の参拝者用無料駐車場は、JR三輪駅の踏切から西へ入った場所に広がっています。大鳥居をくぐると道路の両側に設けられており、アクセスもわかりやすいです。
収容台数は約590台と、規模は大きめ。ただし、祭事などの特別な時期には満車に近づくこともあるため、早めの到着がおすすめです。
●駐車可能台数 普通車約590台
●駐車料金 通常無料(正月特別期間 1月1日~5日は有料)

大神神社のご由緒
奈良県桜井市の三輪山麓に鎮座する「大神神社」は、日本最古の神社と伝えられています。ご祭神は大物主大神で、『古事記』『日本書紀』では大国主神の国造りを助けるため三輪山に祀られたと記されています。本殿を持たず、山そのものをご神体とする古代の信仰形態を今に伝えています。
崇神天皇の時代、疫病が流行した際に「子孫の大田田根子を祭主とし、酒を奉納せよ」という大物主大神のお告げにより、酒を供えたところ疫病が鎮まったという神話も残り、酒造りの神としても信仰を集めています。これにちなみ摂社「活日神社」には酒造りの祖・高橋活日命が祀られています。
古くから朝廷や幕府に篤く崇敬され、延喜式では官幣大社、大和国一之宮、二十二社の一社とされました。現在も拝殿奥の「三ツ鳥居」を通して三輪山を拝み、国造りや生活守護の神として全国からの参拝を集めています。
●ご祭神 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)
●配祀神 大己貴神(おおなむちのかみ)、少彦名神(すくなひこなのかみ)
●ご利益 農業・工業・商業などの産業開発、交通・航海、縁結び、酒造り、製薬・病気治癒など
ここから「大神神社」の参拝リポートがスタート!
三輪山を仰ぐ古社【大神神社】の見どころ
今回の目的地は奈良県桜井市の「大神神社」だ。奈良市から国道169号を走っていると、巨大な大鳥居が見えてきた。これが大神神社の一の鳥居だ。
【大鳥居】三輪の玄関を飾る日本一の偉容
大神神社の入口にそびえるのが、高さ32.2メートル、柱の間23メートルを誇る巨大な「大鳥居」。実際に間近で見上げると首が痛くなるほどの大きさで、その迫力に思わず立ち止まってしまう。まさに日本でも最大級のスケールだ。
この大鳥居は、昭和59年の昭和天皇御親拝を記念し、昭和61年に建立されたもの。車道をまたぐ鳥居としては日本一の大きさを誇るらしい。材質には耐候性鋼板が用いられ、耐久年数はおよそ1300年ともいわれているそうだ。時を越えて人々を迎えるにふさわしい、大神神社の壮麗な玄関口である。

【一の鳥居】不意に現れる線路と神域への道
参道からは少し外れた場所に建っているため、初めて訪れる人には見つけにくいのが「一の鳥居」。実際、私も最初は気づかずに通り過ぎてしまい、戻って探すことになった。

参道を歩いていくと「こんなところに線路が!」
なんと、参道の途中に電車の線路が横切っている。神社の参道に電車が走っている光景は不思議だ。

【献酒樽】酒の神に捧げる樽と「杉玉」の発祥地
二の鳥居の手前には、全国の酒蔵から奉納された酒樽がずらりと並んでいた。この壮観な光景は、大神神社が「酒の神様」として篤く信仰されてきた証でもある。
ご神体・三輪山は古く「三諸山(みむろやま)」と呼ばれ、「みむろ(実醪)」とは「酒の素」を意味する言葉。『日本書紀』には、疫病が流行したとき大物主大神が崇神天皇の夢に現れ、「子孫の大田田根子を祭主とし、酒を奉納せよ」と告げたという神話が記されている。天皇が急ぎ酒を造り捧げると、たちまち疫病は鎮まったと伝わる。この伝承から、大神神社は酒造り信仰の聖地とされてきたそうだ。

ちなみに酒蔵や飲食店の軒先に吊るされるのが「杉玉(酒林)」。新酒ができた合図として青々とした杉の葉で作られ、やがて色が移ろい、酒の熟成を知らせる役割も担う。
実はこの杉玉の発祥は、ここ大神神社にあると伝えられている。三輪は古くから酒造りの聖地であり、酒造に欠かせない杉の神木を祀ってきたことから、この文化が生まれたと言われているそうだ。
大神神社で授与される杉玉には「志るしの杉玉」「酒の神様 三輪明神」と刻印されており、酒の神にゆかりある特別な印として、今も全国の酒蔵に届けられているという。

【二の鳥居】木々に抱かれる神聖な参道
この日は土曜日だったこともあり、多くの参拝者が訪れていた。ここまでの参道の雰囲気とは少し変わり、二の鳥居の向こうには木々に囲まれた参道がまっすぐ続いている。

石や鉄の鳥居とは違い、森の緑と自然に溶け込む姿が印象的だ。

二の鳥居をくぐると木々に囲まれた参道が続き、ひんやりと涼しく感じる。木漏れ日の中を歩くと、マイナスイオンに包まれているようで、自然と神聖な空気に包まれているような気がする。

【祓戸(はらえど)神社】参拝前に心身を清める第一歩
二の鳥居をくぐり、玉砂利の参道を進むと最初に現れるのが「祓戸神社」だ。その名のとおり、参拝者の罪や穢れを祓い清める神々を祀る社であり、大神神社に参拝する際は、まずここで心身を整えるのが慣わしらしい。
祀られているのは、大祓詞にも登場する四柱の神々。小さな社殿ながら、参道の入口に位置することで「ここから神域へ入る」という心構えを与えてくれる存在である。清らかな心身で本社へ進むための第一歩として、参拝時には必ず立ち寄り、二拝二拍手一拝の作法で祈るべき場所である。
●ご祭神:瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)、速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)、気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)、速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)

【夫婦岩(めおといわ)】大物主大神と姫神の恋物語を伝える磐座
祓戸神社を過ぎて参道を進むと、左手に二つの岩が寄り添うように並ぶ「夫婦岩」が現れる。仲睦まじいその姿から縁結びや夫婦円満のご利益があると伝わっているそうだ。
この岩は古くから神が宿る「磐座(いわくら)」として信仰され、室町時代の絵図にも「聖天石」として描かれているという。夫婦和合の象徴であるインドの神「聖天」にちなんだ名とされ、神仏習合の名残を伝えているものと考えられている。

何よりも重要なのは、大神神社に伝わる「三輪山説話」と深く結びついていること。活玉依姫のもとに夜な夜な通った美しい若者が、実は大物主大神であったという恋物語だ。その愛の証として生まれた娘は、のちに初代天皇・神武天皇の后となったとされる。夫婦岩はこの神話を今に伝える古跡とされ、良縁や恋愛成就を願う人々からの信仰を集めているという。
この日も夫婦やカップルが寄り添いながら祈りを捧げる姿も見られた。これから縁を望む人も、すでにある縁を深めたい人も、この夫婦岩の前で祈れば、そのご利益を感じられるのではないだろうか。

【手水舎】
参道を進むと現れる手水舎では、蛇の口から水が!
多くの神社では竜が使われていることが多い印象だが、大神神社は蛇。ご祭神・大物主大神が『古事記』や『日本書紀』で蛇の姿に化身したと伝えられていることにちなんでいるのだろう。


大神神社の参拝におすすめ!白蛇皮風御朱印帳
白蛇伝説ゆかりの大神神社にふさわしい、白蛇の鱗を思わせる型押しデザインの御朱印帳。縁結びや開運を願う参拝をより特別にしてくれる一冊です(^^)!
【衣掛杉(ころもがけのすぎ)】神が姿を現した伝説の杉
手水舎から拝殿へ向かう石段の手前を右に進むと現れるのが「衣掛杉」だ。能楽の謡曲『三輪』にも登場する舞台として知られる。

かつて興福寺に仕えていた僧・玄賓僧都(げんぴんそうず)は、世俗の欲を捨てて三輪山のふもとに庵を結んでいた。そこへ度々訪れては花や水を求めた美しい女性がいたという。
秋のある日、その女性は「寒さをしのぐ衣をください」と願い、僧都は快く衣を渡した。しかし後を追っていくと、その衣は杉の枝に掛かっており、女性の姿は消えていた。実はその女性こそ、三輪の神の化身であったと伝えられている。
【拝殿への石段】古式ゆかしき注連柱が迎える参道
拝殿へと続く石段を一歩ずつ上がっていくと、空気が一段と清らかに感じられる。

石段の上に立つのは、横木(笠木)を持たず、2本の柱に注連縄を渡した古式の「注連柱(しめばしら)」。鳥居の原型ともいわれるこの姿は、神域と俗界を分かつ結界を示しているのだそうだ。
一般的な鳥居とは異なる素朴で力強い佇まいは、まさに古社・大神神社ならでは。初めて目にしたとき、時代を超えて受け継がれてきた神祀りの起源を垣間見た気がした。

【重要文化財・拝殿】三輪山を仰ぐ原初の神まつりの姿
大神神社の拝殿は、寛文4年(1664年)に徳川4代将軍・家綱によって再建されたとされる建物で、国の重要文化財に指定されている。白木造りの切妻造で、幅17m・奥行き8mの堂々とした姿を見せている。檜皮葺の屋根や唐破風の向拝が印象的で、江戸時代の社殿建築らしい力強さを感じさせる。

この神社には本殿がなく、拝殿を通してご神体である三輪山を拝むのが特徴だ。拝殿の奥には「三ツ鳥居」と呼ばれる特別な鳥居があり、古来より神聖な結界として大切にされてきた。3つの鳥居を組み合わせた独特の形は全国でも珍しく、ここから三輪山を拝むことで古代の神まつりの姿を今に伝えている。
さらに三輪山には古代祭祀の跡が数多く残り、勾玉や須恵器などの出土品が祭祀の歴史を物語っている。そうした信仰の積み重ねにより、大神神社は国造りの神を祀る大和国一之宮「三輪明神」として長く親しまれてきたのだという。
いまも医薬や酒造、厄除けなど暮らしを守る神様として、地元の人々には「三輪さん」と呼ばれ親しまれているほか、近年はパワースポットとして若い参拝者にも人気を集めているようだ。

【幣帛料(へいはくりょう)立札】参拝者自身が行う清めの儀式
拝殿のそばに「幣帛料」と書かれた立て札が立っている。ここは、自らを清める「自祓い(じばらい)」を行う場所なのだそう。
作法はまず一礼し、自祓い串を頭上にかざして左→右→左と振りながら、「幸魂奇魂守給幸給(さきみたま くしみたま まもりたまえ さきはえたまえ)」と3回唱える。神職に祓ってもらうのではなく、自分の手で心身を清めるのは新鮮で面白かった。

【社務所・御朱印授与所】
参拝を終え、いよいよ御朱印をいただきに向かう。お守りや絵馬、おみくじなどを販売している社務所に隣接する形で御朱印授与所が設けられている。
この日は多くの参拝客でにぎわっていた。

御朱印授与所もかなり混んでいた。

古社にふさわしい凜とした表情。大神神社の御朱印
大神神社でいただける御朱印は、「大神神社」「大和国一之宮」の文字と参拝年月日が記された、たいへんシンプルで凛とした一枚。直書きで、初穂料は500円である。
このほかにも、日本画家・清水桃香氏が描いた書き置きの御朱印もあり、樹齢400年を超える「巳の神杉」越しに拝殿(重要文化財)が描かれた趣あるデザインとなっている。伝統の中に現代の感性が調和した特別な御朱印として人気を集めているようだ。

お目当ての御朱印も無事いただけたので、境内を散策することに。
【参集殿】幸運を招く「なで兎」をナデナデ
拝殿の左手に建つ「参集殿」に立ち寄る。その玄関で参拝者を迎えてくれるのが、愛らしい「なで兎」だ。大神神社のご祭神・大物主大神は『古事記』の「因幡の白うさぎ」を助けた神としても知られ、兎とは古くから深い縁を持つ。

この「なで兎」は江戸時代に一の鳥居前の大灯籠を守っていた石兎が由来とされ、撫でると運気が上がるだけでなく、撫でた部分の痛みを和らげてくれると伝えられている。多くの参拝者に撫でられているせいか、その身体はいつもピカピカに輝いている。私も「いいことありますように」と念を込めながらいっぱい撫でてみた。
大神神社では古くから卯の日を特別なご神縁の日として大切にしており、今も毎月「卯の日祭」が行われているそうだ。参集殿を訪れたら、ぜひこの「なで兎」を撫でて、そのご神助にあずかっていただきたい。

【巳の神杉(みのかみすぎ)】白蛇の伝承が息づくご神木
拝殿の前にそびえる巨木「巳の神杉」は、大神神社を象徴するご神木の1つ。大物主大神が白蛇の姿に変じて現れるという伝承にちなみ、この杉の洞には昔から白蛇が棲むとされている。姿を見られることは非常に稀だが、もし出会えたなら大きな幸運に恵まれるといわれている。
蛇は古来より三輪の神の化身とされ、水や雷をつかさどる農業神、五穀豊穣の神としても信仰を集めてきた。杉そのものも「神の宿る木」「霊木」として崇められ、今も参拝者が絶えない。
この神杉の前には、白蛇の好物である卵や神酒が参拝者によって供えられている。その姿は江戸時代の『大和名所図絵』(1791年)にも描かれており、現在の木は樹齢500年を超えると伝えられる。また、かつては「雨降杉」とも呼ばれ、雨乞いの祈りが捧げられていたという。
参拝の折には、卵を供える人々の信仰心や、今もなお大切に守られてきた神秘的な伝承に触れることができるだろう。
それにしてもお供え物に卵とは珍しい。一応白蛇を探してみたが…やはりいなかった。

【神宝(かんだから)神社】財宝を守り、繞道祭の始まりを告げる社
拝殿の右手奥に鎮まる「神宝神社」は、大神神社の末社として知られるお社。御祭神は熊野三山(熊野本宮・那智・速玉)の神々で、古絵図には「熊野権現」として描かれているそうだ。社名のとおり、お宝や財産を守る神として古くから厚い信仰を集めてきたという。
この神社は、毎年元日の深夜に行われる大神神社の大祭「繞道祭(にょうどうさい)」とも深い関わりを持つ。拝殿で御神火を灯した大松明が氏子たちによって境内の摂末社18社を巡るが、その最初に祭典が行われるのがこの神宝神社。新年を告げる大和の年中行事において、まさに切り込み隊長のような役割を担っているのだ。
御例祭は毎年5月9日。三宝荒神の信仰も篤く、大神神社を訪れる際にはここに必ず立ち寄る参拝者も多いのだとか。財宝守護の御神徳に加え、年の始まりを彩る神事と結びついた特別な存在感を放つ社である。
●ご祭神 家都御子神(けつみこのかみ)、熊野夫須美神(くまのふすみのかみ)、御子速玉神(みこはやたまのかみ)

【天皇社(てんのうしゃ)】崇神天皇を祀る静かな社
拝殿の南側の小高い場所にひっそりと鎮まるのが「天皇社」だ。祀られているのは崇神(すうじん)天皇。三輪山麓の磯城瑞籬宮(しきみずがきのみや)に都を置き、国の基盤を整えた天皇として讃えられる聖帝である。
崇神天皇は敬神の念が篤く、天照大御神を皇居から倭笠縫邑(現在の桧原神社)へ丁重に遷し、神社制度を整えた最初の天皇とされる。産業や交通を発展させ、国民の暮らしを豊かにした数々の事績からも、大和朝廷の基盤を築いた重要な人物だったと考えられている。
天皇社の社殿の背後には三輪山がそびえ、清らかな空気が漂っていた。階段を上がった先に垣に囲まれた祠が静かに佇み、訪れる者を厳かな気配で包み込む。毎年11月14日には「崇神天皇奉讃祭」が執り行われ、神楽「磯城の舞」が特別に奉奏されるらしい。
●ご祭神 崇神天皇

【三輪成願稲荷(みわじょうがんいなり)神社】商売繁盛と念願成就の祈り
拝殿から南へ、三輪山の平等寺へ向かう道の途中に鎮座するのが「三輪成願稲荷神社」である。創祀は鎌倉時代の正応3年(1290年)。元々は大神神社の神宮寺のひとつだった尼寺・浄願寺の鎮守社として始まったと伝えられている。
ご祭神は稲荷の神で、食物をつかさどり、商売繁盛や開運招福、念願成就のご利益があるとされる。境内には稲荷社らしく鳥居が連なり、伏見稲荷の千本鳥居ほどの規模ではないが、その雰囲気を受け継いでいる。
御例祭は毎年3月の初午(はつうま)の日に行われ、参列者には昔懐かしい「旗飴(はたあめ)」が配られるそうだ。地域の人々に親しまれてきた素朴で温かな信仰の風景が、今も残されている。
●ご祭神 宇迦御魂神(うかのみたまのかみ)

三輪はそうめん発祥の地!参拝ついでに立ち寄りたいお店
奈良県桜井市・三輪は、大神神社のある町であり、じつは「そうめん発祥の地」といわれている。三輪山の清らかな水と良質な小麦から作られるそうめんは、細く長い形から「長寿」を象徴する食べ物として親しまれてきた。
境内の近くには老舗のそうめん店が多く立ち並び、参拝とあわせて三輪そうめんを味わうのも楽しみのひとつである。
【そうめん處 森正】歴史を感じる店構えでいただく地元グルメ
今回私が立ち寄ったのは「そうめん處 森正」。外観から歴史を感じさせる佇まいで、雰囲気がよい。実際に訪れた感想をレビューとしてまとめてみたい。

店内は冷房こそ扇風機だけであったが、冷えたおしぼりを出してくれる心遣いがありがたく、暑さの中でほっと一息つけた。お店の方の対応も丁寧で気持ちがよかった。

注文したのは「冷たいそうめんと柿の葉寿司(3個)セット」。氷に盛られたそうめんは見た目にも涼しげで、つるりとした喉ごしが暑い日にぴったりである。海老やしいたけ、錦糸卵が彩りを添え、素朴ながらも美しい一皿だった。
柿の葉寿司は奈良の名物で、塩で締めた鯖などを酢飯にのせ、柿の葉で包んだ押し寿司。包みを開いた瞬間に広がる香りが印象的で、さっぱりとした味わいがそうめんとの相性も抜群であった。

そうめんを待つ間にいただいた奈良の地酒「春鹿(はるしか)」もまた格別。すっきりと飲みやすく、ほんのりとした甘みが口に広がる。冷えた一杯は暑い日に心地よく、食前酒にちょうどよい軽さであった。大神神社が酒の神としても信仰を集めてきたことを思えば、この地で味わう地酒はひとしおである。

《そうめん處 森正の基本情報》
【そうめん處 森正の所在地】
〒633-0001 奈良県桜井市三輪535
【そうめん處 森正の電話番号】
0744-43-7411
【そうめん處 森正の営業情報】
●営業時間
平日:10:40~15:30、土曜日:10:30〜16:00、日曜日:10:00~16:00、祝日:10:30~16:00、朔日:7:45~13:30(天候等により、早く閉店する場合もあり)
●定休日 月・火曜日(祝日は営業)
【名物みむろ】参拝のお土産ならこれ!大神神社ゆかりの老舗最中
参拝のお土産に選んだのは、大神神社の名物「みむろ最中」。あんには奈良県産の大和大納言小豆が使われ、こしあんと粒あんを別々に炊き上げた後に合わせる「鹿の子あん」が特徴で、なめらかさと粒の食感を同時に楽しめる逸品だ。
製造元は、弘化元年(1844年)創業の老舗「白玉屋榮壽」、読み方は「しらたまやえいじゅ」だ。店舗は大神神社のすぐ近くにあり、御神体・三諸山(みむろやま)にちなんで名付けられた。宿場町として栄えた桜井市三輪で評判を呼び、今では奈良を代表する銘菓のひとつとなっている。
もち米でつくられた皮は香ばしく、パリッとした歯ごたえが心地よい。すっきりとした甘さのあんと相性抜群で後味も軽やか。何度でも食べたくなる素朴な美味しさだ。参拝帰りのお土産や贈り物にもぴったりの一品である。

《白玉屋榮壽 本店の基本情報》
【白玉屋榮壽 本店の所在地】
〒633-0001 奈良県桜井市大字三輪497
【白玉屋榮壽 本店の電話番号】
0744-43-3668
【白玉屋榮壽 本店の営業情報】
●営業時間 8:00~19:00
●定休日 月曜日、第3週のみ月曜・火曜日(月曜日が祝日の場合は営業、翌日休業)
白蛇伝説にちなんだ一冊!大神神社にぴったりな御朱印帳
今回のリポートはいかがでしたか?
大神神社といえば、ご祭神・大物主大神が白蛇の姿で現れたという神話で知られています。その伝承にちなみ、参拝のおともにぴったりな一冊としてセレクトしたのがこちら。
白蛇皮風 御朱印帳
白蛇の鱗を思わせるリアルな型押しが施され、まるで本物のような質感を再現した特別な御朱印帳です。縁起のよい白蛇柄は、古来より金運・開運の象徴とされ、大神神社の白蛇信仰とも深く重なります。

中紙には、墨の乗りがよくにじみにくい奉書紙を使用。蛇腹式で見開きも美しく、日本製ならではの丁寧な仕立ても魅力です。丈夫で持ち歩きやすく、長く大切に使える一冊となっています。
参拝の記録を刻むだけでなく、白蛇のご加護を感じながら特別なご縁を重ねていけそうな御朱印帳。大神神社の参拝や、開運を願う御朱印めぐりにぜひおすすめしたい一冊です(^^)

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!
神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!
せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?
これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!
さらに!さらに!!
日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」
そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
詳しくは下記のページをクリック♫
日宝綜合製本株式会社
岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)






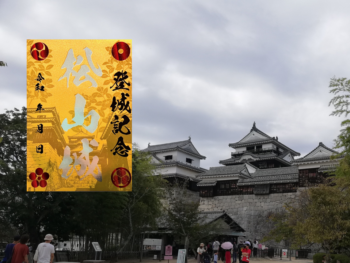


 【新薬師寺】の見所と御朱印!国宝の薬師如来と十二神将に出会う古刹
【新薬師寺】の見所と御朱印!国宝の薬師如来と十二神将に出会う古刹